地上権が消える?分収造林裁判でびっくりの判決
名古屋高等裁判所で、先月興味深いというか、びっくりの判決が出た。
内容は「分収造林」に関するもの。石川県金沢市の原告が、1968年に山林23ヘクタールを県の林業公社と契約して造林が行われた。主伐までの期間は40年~45年だった。つまり2013年に期限は来たのだが、公社側は主伐をせず、さらに35年間の契約延長を求めた。
原告は契約延長を拒み、公社権利分の樹木を伐採して明け渡しを求めた……というのが裁判の内容。金沢地裁は請求を棄却したので控訴していたのである。
そして出た高裁判決の中に、造林木はみんな原告のもの、という文言があったのだ。その理由は契約終了時に公社側の地上権は消滅しているから。公社は上告しなかったようだから、判決は確定している。
これがびっくり判決だというのには、少々説明がいる。
まず分収造林とは、山の所有者から土地を借りて造林し、木が育つと伐採して得た収益を分配する林業界特有の仕組みだ(今回の事例では原告:公社=4:6)。契約期間中は、植えた木々の権利は共有扱いだが、実質的に山林は公社が管理することになる。
だが造林した時代から木材価格は大きく下がり、現時点で伐採しても赤字の恐れが強い。そこで契約を延長して、木をより太く育てて木材が高く売れるまで待とう……というのが公社側の説明だ。
だが納得しない土地所有者は多い。長期間すぎるし、土地を実質的に公社に占有されたままだからだ。もちろん地代は支払われない。
ここで今回の裁判の個別の事情や、分収造林そのものの問題を詳しく取り上げる余裕はないが、私が驚いたのは「契約終了後は、造林木もすべて土地の所有者が取得する」とした判決理由である。
林業界では、歴史的に土地と地上に生える樹木の権利を分けて考える。また土地よりも樹木こそが財産だとする意識も強かった。そこでは、造林木は植えて育てた者の所有と考えるのだ。
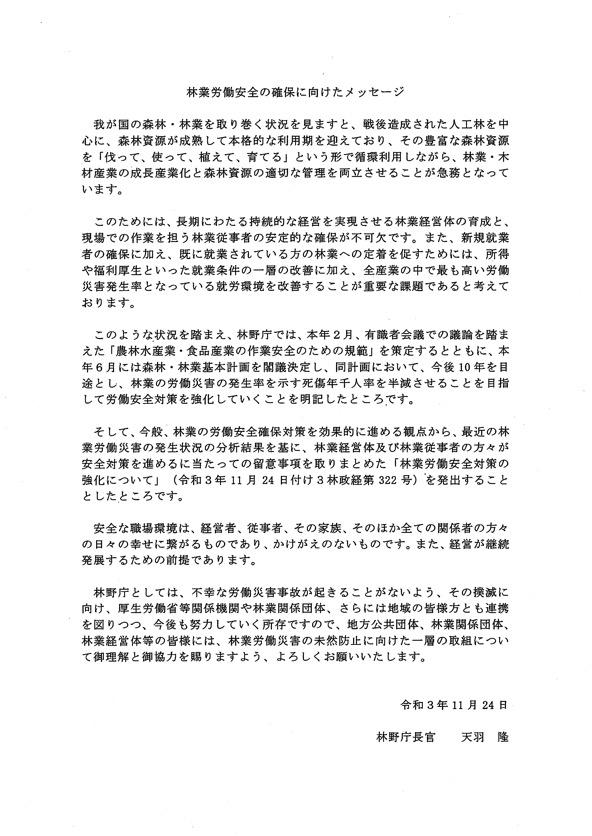
だから借りた土地に造林して育て、収穫した木材の利益を折半することは多い。たとえば奈良の吉野林業は、借地林業と呼ばれるほどだ。この仕組みが外部から造林資金を呼び込む役割を果たしてきた。
こうした事情を受けて、立木を土地とは別に登記する法律もつくられている。(民法の「立木ニ関スル法律」。明治42年制定)
この法律は今も生きている。登記された立木は、土地と分離して譲渡したり、抵当権を設定したりすることもできる。さらに土地所有権または地上権の処分の効力は、登記を受けた立木には及ばないとする。これは立木がある間(伐採するか枯れてしまうまで)有効だ。
だから今回の高裁判決は、びっくりなのだ。契約が終われば(立木を含む)地上権が自動的に土地所有者のものになってしまう(分収林の立木は登記していなかっただろうが、従来の慣習的な権利とされたものが消えてしまう)。
今後、分収造林を行った各地で、同様の事例が相次ぐかもしれない。契約延長に同意せずに期間を超えたら、地上権は土地所有者に移ると見なされるのなら、そちらを選ぶ人も出るだろう。
とはいえ分収造林問題の解決にはならないはずだ。所有者はいくら造林木を全部手に入れたとしても、伐採しようとすれば改めて業者に発注しなければならないが、赤字必至だからだ。仮に伐採したら、はげ山になって災害を招きかねないし、跡地に再造林できるかどうかも怪しい。
結局は経営を放置するか、土地ごと山林を売却するか(買い手が見つかったとして)しかないのではあるまいか。ほかに自治体に委託する方法もある(森林経営管理法)が、これでは公社から取り戻した山林が今度は自治体に渡るだけなのだから、意味がない。自治体も税金を投入しなければならなくなる。
一方、公社にとっては造林にかけた経費を回収することなく明け渡すのだから赤字が確定する。これは隠してきた負債が明るみに出ることを意味する。
以前、朝日新聞が全国の林業公社にアンケートを行ったところ、債務に対する時価評価額は4%にすぎなかったという。(2018年5月6日紙面)
全国の林業公社の分収造林面積はおよそ42万ヘクタールにも及ぶが、その隠れ負債は1兆円を優に超えるだろう。それらが表に出て白日の元にさらされてしまう。だから契約延長したがるわけだが、仮に30年以上先送りしても、その時期に木材価格が上がっている保証はない。逆に負債が膨れ上がっている可能性だってある。
ことは自治体の分収造林だけではない。国も分収造林、分収育林(緑のオーナー制度として知られたもの)で莫大な(隠れ)負債を抱えていると思われる。
今回の判決は、林業界の従来の造林木に関する意識を変えるだけでなく、隠れ負債というパンドラの箱を開けるきっかけになるかもしれない……と私は感じたのである。








